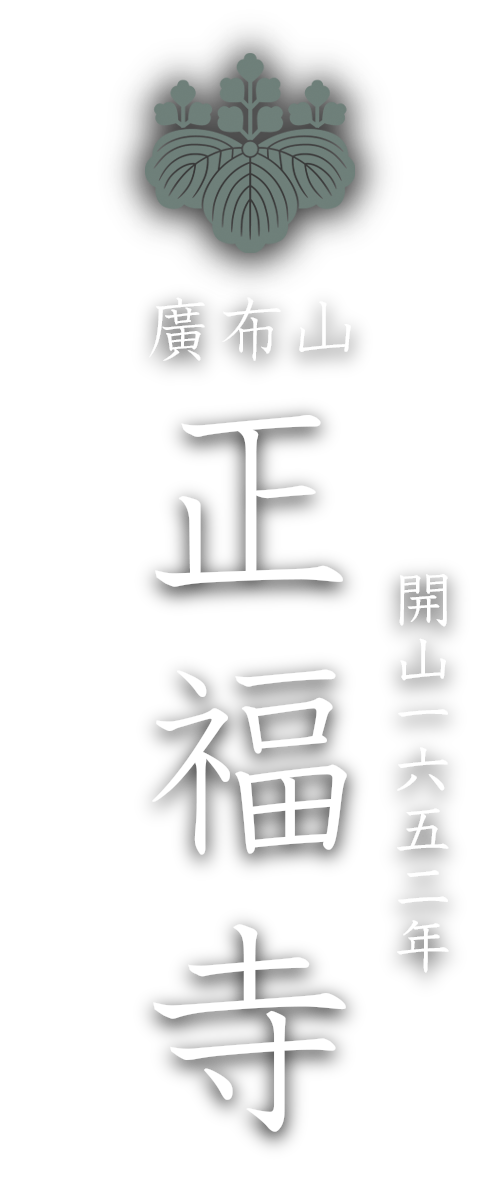一六五二年開山
三百七十余年続く町のお寺
忘れかけていたうつろいゆく季節の匂い
植物の儚い美しさ
流れる優しい水の音
ふと淋しくなって涙を流したり
楽しかった思い出にふれ懐かしむ
そんなとき手を合わせ自分と向き合い
大切だった人と心で繋がる
旅立たれた方は色んなことを教えてくれる
その声に耳を傾けたとき
そんなほんの少しの時間が心を穏やかにする
1652年開山
三百七十余年続く町のお寺
忘れかけていたうつろいゆく季節の匂い
植物の儚い美しさ
流れる優しい水の音
ふと淋しくなって涙を流したり
楽しかった思い出にふれ懐かしむ
そんなとき手を合わせ自分と向き合い
大切だった人と心で繋がる
旅立たれた方は色んなことを教えてくれる
その声に耳を傾けたとき
そんなほんの少しの時間が心を穏やかにする
三百七十余年続く町のお寺
忘れかけていたうつろいゆく季節の匂い
植物の儚い美しさ
流れる優しい水の音
ふと淋しくなって涙を流したり
楽しかった思い出にふれ懐かしむ
そんなとき手を合わせ自分と向き合い
大切だった人と心で繋がる
旅立たれた方は色んなことを教えてくれる
その声に耳を傾けたとき
そんなほんの少しの時間が心を穏やかにする
写真で見る正福寺
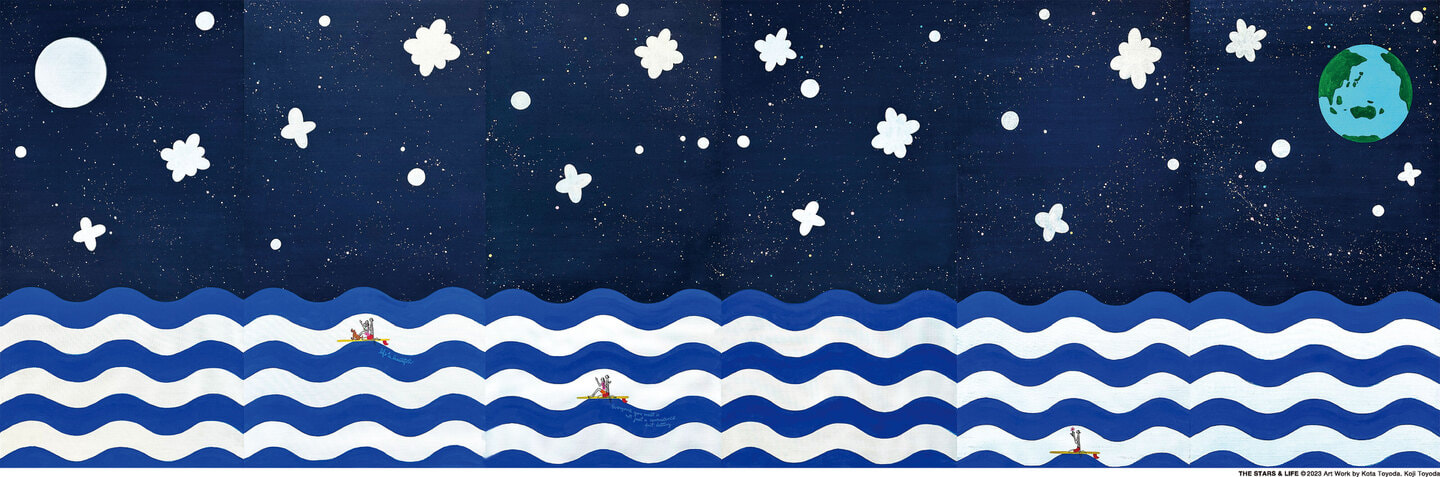
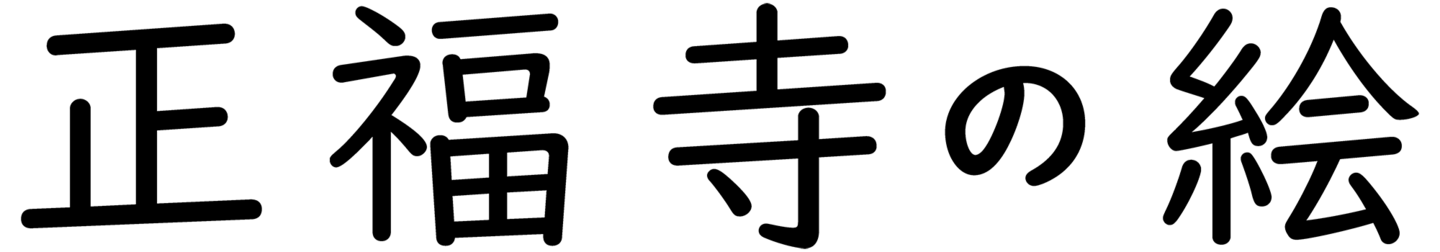
豊田弘治氏、豊田弘大氏によるコラボ作品を現代アートの襖絵として表現して下さいました。豊田弘治氏による「LIFE」という波を人生に例えた作品と豊田弘大氏が表現する「THE STARS」を合わせたスケール感ある作品。テーマは、『ご縁を大切にする』ということで、この襖絵をご覧になってくださる方々も何かのご縁でご覧くださっていると思います。そうなんです。その積み重ねが人生だということをこの襖絵にそんな想いを込めています。